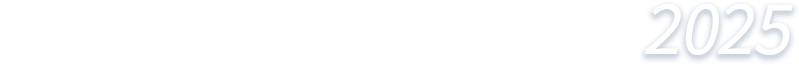本会議1日目
講演テーマ・講演者紹介
日本のソフトウェア産業競争力を考える
登壇者
飯塚 悦功 氏概要
 ソフトウェア製品は長いこと大幅な輸入超過であり今後もその見通しだが、IT生産高の自給率は90%を優に超える。これらを競争力の指標にするのは適当ではない。まず、ソフトウェア産業競争力は、ソフトウェアによって生み出される社会・経済にもたらず価値を通して理解すべきことを再確認する。次に、この認識のもと、わが国のソフトウェア産業競争力の考察のため、競争力視点でのソフトウェア製品の特徴、ソフトウェアによる価値創造・提供の因果構造、そして日本や日本人の強み・特徴の理解が基本となることを再認識する。これらの考察を踏まえ、わが国のソフトウェア産業競争力強化への処方箋を愚考してみたい。
ソフトウェア製品は長いこと大幅な輸入超過であり今後もその見通しだが、IT生産高の自給率は90%を優に超える。これらを競争力の指標にするのは適当ではない。まず、ソフトウェア産業競争力は、ソフトウェアによって生み出される社会・経済にもたらず価値を通して理解すべきことを再確認する。次に、この認識のもと、わが国のソフトウェア産業競争力の考察のため、競争力視点でのソフトウェア製品の特徴、ソフトウェアによる価値創造・提供の因果構造、そして日本や日本人の強み・特徴の理解が基本となることを再認識する。これらの考察を踏まえ、わが国のソフトウェア産業競争力強化への処方箋を愚考してみたい。
業務上の経験や研究を主とした経歴
1947年生。1970年東京大学工学部計数工学科卒。1974年修士修了。電気通信大学助手、東京大学助手、講師、助教授を経て、1997年東京大学工学系研究科教授。2008年医療社会システム工学寄付講座特任教授。2012年上席研究員、名誉教授。2013年東京大学退職。2016年JAB理事長。工学博士。学部・修士での専門は統計解析。その後の主たる研究分野は品質マネジメント。品質マネジメントにおける主要な関心領域は、TQM, ISO 9000, 構造化知識工学、医療社会システム工学、ソフトウェア品質、原子力安全。
研究論文や著書
飯塚(2008):Q-Japan~よみがえれ、品質立国日本、日本規格協会。飯塚(2009):現代品質管理総論、朝倉書店
飯塚・金子龍三(2012):原因分析~構造モデルベ-ス分析術、日科技連出版
飯塚(2013):品質管理特別講義(基礎編)+(運営編),日科技連出版社
飯塚他(2014):進化する品質経営~事業の持続的成功を目指して、日科技連出版
飯塚・金子雅明他(2018):ISO運用の大誤解を斬る、日科技連出版
飯塚・金子雅明他(2021):TQMの大誤解を斬る(みんな編)+(トップ編)、日科技連出版
飯塚(2023):マネジメントシステムに魂を入れる、日科技連出版
その他(学位、表彰、学会活動、その他特記事項)
日本品質管理学会元会長(03-05)、デミング賞審査委員会元委員長(08-11)、日本経営品質賞委員会委員(06-)、IAQ Academician(07-), TC176元日本代表(00-12)、JAB/MS認定委員会元委員長(99-12)、JAB元理事長(16-24)、医療の質・安全学会元理事(06-20)、SESSAME理事長(00-25)、JUSE/SQiP前委員長(94-12)2006年度デミング賞本賞
1996, 98, 99, 2002, 03, 06, 09×2, 12, 14, 15, 19年度日経品質管理文献賞
2010年ASQ(アメリカ品質学会)Freund-Marquardt Medal(国際標準化)
2012年工業標準化内閣総理大臣表彰
”わかる”から”使える”へ
~シフトレフトのための実践ガイドと適用事例の紹介
登壇者
加茂 悠 氏共著
田口 真義 氏リコーITソリューションズ株式会社小笠原 倫子 氏リコーITソリューションズ株式会社
齋藤 寛典 氏リコーITソリューションズ株式会社
滑川 梨紗 氏リコーITソリューションズ株式会社
 製品・サービス開発の現場では、企画・開発・評価担当者が連携し、「低コストで迅速に市場へ価値ある製品・サービスを提供する」ことを目指していますが、実際には、工程が進むにつれ、改善提案が納期やコストの制約で先延ばしになったり、完成品が企画担当者の想定と異なるケースが発生します。その結果、顧客に届けたい価値が十分に実現されない、余計な手戻りや市場対応が必要になるなど、本来目指すべき開発のスピードやコストから乖離が生じることがあります。これらの問題を解決するには、開発の初期段階に要求を分析・検証することが重要であり、特に利用者視点を持つ評価担当者が関与するシフトレフト活動が効果的です。ただし、進め方がわからない、効果が不明確、コストが増えるのではといった不安から、導入には障壁があります。そこで我々は、評価担当者が開発の初期段階で要求を分析・検証する手法として「品質要求分析」を考案しました。この手法は、現場の理解、仮説の立案、要求の検証・提案、テスト要求の導出という4つのステップで構成され、利用者の観点からの不整合や抜け漏れを早期に検出し、必要な機能や改善案を具体化することで、後工程での手戻りや仕様のずれの未然防止を支援します。本発表では、この手法を用いた取り組みと、その効果を事例とともに紹介します。
製品・サービス開発の現場では、企画・開発・評価担当者が連携し、「低コストで迅速に市場へ価値ある製品・サービスを提供する」ことを目指していますが、実際には、工程が進むにつれ、改善提案が納期やコストの制約で先延ばしになったり、完成品が企画担当者の想定と異なるケースが発生します。その結果、顧客に届けたい価値が十分に実現されない、余計な手戻りや市場対応が必要になるなど、本来目指すべき開発のスピードやコストから乖離が生じることがあります。これらの問題を解決するには、開発の初期段階に要求を分析・検証することが重要であり、特に利用者視点を持つ評価担当者が関与するシフトレフト活動が効果的です。ただし、進め方がわからない、効果が不明確、コストが増えるのではといった不安から、導入には障壁があります。そこで我々は、評価担当者が開発の初期段階で要求を分析・検証する手法として「品質要求分析」を考案しました。この手法は、現場の理解、仮説の立案、要求の検証・提案、テスト要求の導出という4つのステップで構成され、利用者の観点からの不整合や抜け漏れを早期に検出し、必要な機能や改善案を具体化することで、後工程での手戻りや仕様のずれの未然防止を支援します。本発表では、この手法を用いた取り組みと、その効果を事例とともに紹介します。
事業分析におけるSysMLを用いた競争優位性の分析支援手法の提案
登壇者
髙附 翔馬 氏共著
梅田 浩貴 氏国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構植田 泰士 氏国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
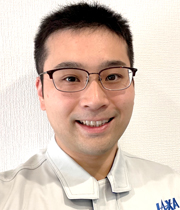
近年宇宙開発のコモディティ化は進み、宇宙機システムを開発できる企業が増えたため、開発したシステムは誰にどのような価値を提供するのか、といった顧客向けサービスの構築により優位性を確保する重要性が増加している。特に我々が設計対象としている地球近傍の宇宙機システムを利用したサービスは以下の特性を有する。
- 【特性1】市場拡大期であり新規技術で市場を開拓中
- 【特性2】価値連鎖が多くの分野に渡る(例:宇宙機システム事業者-データ提供事業者-データ利用事業者)
- 【特性3】物理制約等に依存しシステムに多くの制約がある
- 【課題】競争優位性のある属性(性質や特徴を示すパラメータ)の特定が困難
宇宙機システムは大規模かつ複雑性があるため、分野横断的にシステムを捉えることができるMBSE(モデルベースシステムズエンジニアリング)によって、システム開発を実施するプロセスに変革しつつある。
そこで、顧客の特定やサービスの提供時でも同様のアプローチ(MBSE の適用)によって、競争優位性のある属性を特定可能か検討した。顧客がサービスを利用するシナリオやサービスと顧客事業の因果関係の分析を支援するモデリングルールと分析ガイドからなる分析手法を構築した。
本発表ではその内容を紹介する。
スマート家電における数理モデルを利用した脆弱性評価手法
登壇者
小林 大晃 氏共著
久野 倫義 氏三菱電機株式会社宮内 茂人 氏三菱電機株式会社
中込 友明 氏三菱電機株式会社
藤原 秀治 氏三菱電機株式会社
澤田 賢治 氏大阪大学
岡村 望夢 氏大阪大学

製品仕様を検討する技術者が、セキュリティに対する脆弱性や脅威を把握し適切な対策を検討するには、高度なセキュリティに関する知識を必要とする。
このような状況下において、製品セキュリティの分析は、セキュリティエキスパートに依存することが多くなり、製品仕様を検討する技術者にとって、ブラックボックスになる危険性がある。このような状況を解決するため、製品仕様を検討する技術者が理解しやすく且つ体系的なセキュリティ分析を実施できる手法を提案する。体系的な分析を実現する上で、製品の状態遷移表現にブーリアンネットワークという数理表現を活用することで、既存の脆弱性評価やリスク分析手法の自動化を目指した活動を紹介する。
Coaching and Facilitation Empowerment(CaFE)メソッドによる
自律人材育成
登壇者
片桐 汐駿 氏共著
鵜島 衣里 氏住友重機械工業株式会社
本手法は、育成対象者が指導内容をポジティブに捉え、自律的に行動を起こす動機づけをするアプローチである。シンポジウムの聴講者には、本手法を自組織で実践して育成対象者の育成に役立てるとともに、本手法を通じて、育成対象者を育成促進するために何が必要かを考慮するきっかけとなることを期待する。
我々研究員は、開発現場での業務を通じて、育成対象者に対してプロセス改善に取り組むよう促す指導者の立場である。我々が育成対象者に期待するのは、自ら開発現場の問題を捉え、それに対し自ら分析して改善策を考え、周りを巻き込みながら継続的に活動できる能力である。しかし現状は、ソフトウェア開発に関わるところでは、レビューで何度も同じ指摘を受ける、プロセス改善活動の場で自分の意見を発信しようとしない、といった状況であり、我々の期待レベルから大きくかけ離れている。
この問題解決の仮説として、『自律改善人材を育成するために、指導者層が若手の育成対象者一人ひとりの個性に適したアプローチをとることで、自律的な人材が育成できるのではないか』と考えた。
一人ひとりの個性に適したアプローチをとるために、Coaching and Facilitation Empowerment(CaFE)メソッドを創出した。
シンポジウムの聴講者には、CaFEメソッドを自組織で実践して若手人材の育成に活用いただき、本手法に対してフィードバックをいただけたら幸いである。
プロジェクトマネジメント力強化のための
PM視点の仕組の充実度と実効性の調査事例
登壇者
吉岡 克浩 氏共著
山田 佳邦 氏三菱電機ソフトウエア株式会社
当社では、「品質風土」・「組織風土」・「ガバナンス」の3つの改革を推進している。品質風土改革では「そもそも現場が品質不適切行為を起こす必要のない仕組みの構築」の1つとして、新製品開発プロジェクトにおけるマネジメント力の強化に取り組んでいる。当社は異なる製品群を開発する製作所が複数あり、部門ごとにマネジメント方法が異なるため、全社共通のマネジメント課題を抽出することが急務であった。また、受託システム開発を担う部門ではPMOを設置し効果的なプロジェクト運営やプログラム・ポートフォリオレベルのマネジメント活動をサポートしていたが、それら良好事例を全社で共有する機会がなかった。これらの課題解決に取り組んだ。
調査により共通課題として「プロジェクト憲章の合意」「ベースライン管理の浸透」「マネジメント視点の振返り」が抽出されたため、それらの実施度合いを点数化する仕組みを開発し、複数プロジェクトに適用した。適用結果や改善に活用した事例を紹介する。
機械製造業での外販システム開発部署を中心とした組織行動変革
登壇者
森田 恭平 氏
過去に成功体験を収めてきている機械メーカーにおいて、機械売りに最適化された組織行動からサービス売りを促進できる組織行動への変革が求められている状況です。
VUCA時代の継続的な付加価値提供を可能とする体制整備を目的とし、システム開発内製化を軸に、属人化低減・人材流動性向上を促進する組織行動マネジメントを試みています。
顧客・代理店に対してITソリューションを通じた価値提供を行うSE部署を組織行動変革の核と捉え、当該部署にて次の3つの基盤構築活動を実施しました。
- 知識基盤
- 案件管理基盤
- 教育基盤
これらの取組みにより、これまでの属人的な顧客案件対応、他部署連携が標準化され、再現性のある形で集合知を応用した価値提供を行う体制が整えられます。
実施結果として、定量的効果、定性的効果、両方の側面を紹介いたします。
永らく慢性的に属人化してきた組織文化においては、定量的効果よりも、定性的効果への期待が重要と考えます。
定量的効果としては、属人化低減・人材流動性向上の観点で、自他部署で期待できる年間のコスト削減を紹介いたします。
定性的効果としては、取組みを継続する中で生じた、自他部署を巻き込む形での組織行動の再定義を紹介いたします。
業界や企業の文化に依存する話が多いかもしれませんが、本発表が皆さんの何かの参考になれば幸甚です。
生成AIを活用したテスト網羅度分析手法の検証
登壇者
堀江 眞太 氏共著
小野 寛明 氏日本電気株式会社久田 大地 氏日本電気株式会社
下村 哲司 氏日本電気株式会社
伊藤 拓也 氏日本電気株式会社

ソフトウェア開発におけるテスト技法は、構造ベースと仕様ベースに大別される。構造ベースでは命令網羅や分岐網羅などが網羅性指標として広く用いられる一方、仕様ベース、特に設計仕様に対するテスト網羅性を定量的かつ効率的に評価する手法は少ない。
その背景として設計仕様に対するテスト項目の網羅性を示す評価には二つの課題が存在する。
- 人手で網羅性を直接確認することは、膨大な時間と労力を要すること
- 従来のアプローチでは、主にテスト項目密度などの間接的な指標を用いて網羅性を評価してきたが、この方法では網羅性に説得力が不足すること
本研究はこの課題に着目し、生成AIを活用したテスト観点網羅度分析手法の有効性を検証した。
具体的には、生成AIを用いて開発成果物(開発計画書、設計仕様書、テスト仕様書)からテスト観点を抽出し、各テスト項目の網羅性を自動分析・可視化する仕組みを構築した。異なるソフトウェア製品開発プロジェクト6件のプロジェクトの成果物に対して検証を行い、分析結果の妥当性、テスト項目の「網羅性スコア」の有用性を確認した。一方で、実運用上の課題も明らかとなった。
本発表では、生成AIを用いたテスト観点網羅度分析手法の概要、検証結果、課題と今後の展望を紹介する。
自然言語のテストシナリオから保守性の高いテストスクリプトを自動生成する手法
~Webエージェント技術を活用したアプローチ~
登壇者
切貫 弘之 氏共著
但馬 将貴 氏NTT株式会社若林 慧 氏NTT株式会社
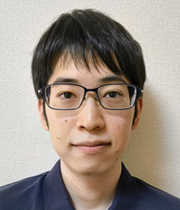 近年、LLMを活用したWebエージェント技術が進化し、ユーザが自然言語で指示を入力するだけでWebブラウザを自動操作できる仕組みが実現しつつある。この技術により、従来多大な手間を要していたE2Eテストのスクリプト作成や保守の効率化が期待される。一方、Webエージェント技術をそのままE2Eテストに適用する場合、実行ごとにテスト手順や結果が変動し得る点や、複雑な画面構成下で操作対象要素の特定が困難となる点などの課題がある。
近年、LLMを活用したWebエージェント技術が進化し、ユーザが自然言語で指示を入力するだけでWebブラウザを自動操作できる仕組みが実現しつつある。この技術により、従来多大な手間を要していたE2Eテストのスクリプト作成や保守の効率化が期待される。一方、Webエージェント技術をそのままE2Eテストに適用する場合、実行ごとにテスト手順や結果が変動し得る点や、複雑な画面構成下で操作対象要素の特定が困難となる点などの課題がある。本発表では、自然言語によるテストシナリオから、BDDで利用されるGherkin形式のテストケースおよびJavaScriptによる実行可能なテストスクリプトを自動生成する手法を提案する。生成されるテストの保守性向上のため、LLMを用いて「ログイン」「商品購入」などの意味単位でテスト手順を抽象化し、シナリオ間での共通処理の再利用やデータ駆動テストへの対応を実現した。さらに、テスト生成における探索過程では、画面上の操作対象をDOMツリー構造に基づいて段階的に絞り込むことで、複雑なWebアプリケーションに対する要素特定精度を向上させている。
提案手法のPoCを実装し、ケーススタディおよびWebエージェント向けデータセットを用いた評価実験によって、その有効性を確認した。本発表では、現状のWebエージェント技術の到達点およびE2Eテストへの具体的応用可能性について紹介する。
生成AI活用による品質評価手法の改善に向けた実践的アプローチ
登壇者
中山 茜 氏共著
平井 佳祐 氏株式会社日立システムズ
本発表では、ソフトウェア開発における品質評価の精度向上を目的とし、生成AIを活用した新たな評価手法について報告する。私は品質保証部に所属しており、ソフトウェア開発の品質を確保する立場にあるが、過去の品質評価ノウハウが十分に活用されておらず、担当者ごとの不良傾向分析における精度のばらつきや工数過多といった課題に直面していた。これらの課題を解決するため、過去のデータや経験値を活用でき、多様な問題パターンに対して迅速な解決策を提供する生成AIを導入した。
具体的に本施策では、過去プロジェクトの資料から懸念事項や品質向上の観点を抽出し、これを"品質ナレッジ"として生成AIに組み込んだ。さらに、バグ票のフォーマット成型や集計をツール化し、生成AIに入力することで、品質評価の精度向上と工数削減を実現した。
実施結果として、生成AIは担当者が評価した結果と同等の懸念事項を出力し、品質評価の精度差を低減することが可能となった。また、生成AIとツールの活用により、摘出不良の傾向把握にかかる時間を約半減させ、削減された工数をさらなる品質向上のための分析に充てることができた。
今後は、"品質ナレッジ"の継続的な蓄積と発展、他業種への展開を図り、当社が手掛ける全業種に対して一元的な評価分析を実現することを目指す。
AIシステムの品質を保証するための開発プロセス整備
登壇者
小森 真紀 氏共著
野口 弘貴 氏株式会社 東芝久連石 圭 氏株式会社 東芝
江原 浩二 氏株式会社 東芝
岡本 渉 氏株式会社 東芝

企業におけるAI利用も広く普及し、ソフトウェア開発へのAI利用、AI自体を製品へ組み込むケースも増えています。社会インフラ関係の製品を開発する自組織では、約25年に渡るSPI活動を通じてソフトウェア開発プロセスの整備・展開を進めてきました。これまでもビジネスニーズの変化に合わせて開発プロセスのバリエーションを順次拡張してきましたが、数年前よりAIを組み込んだ新たな製品を開発するケースが出てきており、AIシステム向けの品質保証プロセスを整備する必要がありました。
AIシステム向けの品質保証プロセスを整備するにあたり、AI品質保証としてのポイントを押さえた上で、現実的に実施可能なプロセスにするという点が課題でした。本取り組みの開始当時は、国内外のガイドラインや法規化の動きが進んでいた時期でもあり、弊社の全社ソフトウェア開発推進部門と連携して取り組みました。全社推進部門がまとめた全社向けのガイドラインや品質保証プロセスを参考にして、自組織向けにテーラリングする形で進めました。自組織の製品の特徴や既存のソフトウェア開発プロセスとの整合性を考慮し、既存プロセスを拡張する形で整備してきました。本発表では、4年間取り組んできたAIの品質保証の観点を実際の製品に適用するための施策を紹介します。
生成AIを利用するシステムの安全性評価を支援するテスト観点表の提案
登壇者
田口 真義 氏共著
伊藤 弘毅 氏三菱電機株式会社 生成AIはUXや企業収益を高める一方、その出力が個人・企業・社会に悪影響を及ぼす恐れもあります。そのため、生成AIを組み込むシステムでは、不適切な情報の出力を防ぎ、安全性を確保する設計が不可欠です。生成AIの安全性の重要性は業界内でも広く認識されており、さまざまな評価指針やベンチマークが公開されています。しかし、生成AIやその応用システムの安全性評価において、開発者の視点から見ると、考慮すべき情報は包括的に整理されていません。そこで我々は、それらの情報を整理し、安全性評価に活用できるテスト観点表を作成しました。本発表では、観点表の概要と有効性の評価結果を紹介するとともに、観点表を活用した安全性評価のテストプロンプトの作成方法についても報告します。
生成AIはUXや企業収益を高める一方、その出力が個人・企業・社会に悪影響を及ぼす恐れもあります。そのため、生成AIを組み込むシステムでは、不適切な情報の出力を防ぎ、安全性を確保する設計が不可欠です。生成AIの安全性の重要性は業界内でも広く認識されており、さまざまな評価指針やベンチマークが公開されています。しかし、生成AIやその応用システムの安全性評価において、開発者の視点から見ると、考慮すべき情報は包括的に整理されていません。そこで我々は、それらの情報を整理し、安全性評価に活用できるテスト観点表を作成しました。本発表では、観点表の概要と有効性の評価結果を紹介するとともに、観点表を活用した安全性評価のテストプロンプトの作成方法についても報告します。
生成AI を用いたレビュー承認自動化に関する研究
Human-AI Agreement Zone(HAZ)の定量的活用
登壇者
松井 高宏 氏 AIの業務適用が進展する現代において、「どこまでAIに判断を任せられるか」は重要な課題である。本研究では、人とAIの判断が一致する領域をHuman-AI Agreement Zone(HAZ)と定義し、それを信頼性スコアとして抽出、AIが主体的に判断する自動化構造を提案する。対象は年間50万件の商品レビューの審査業務である。本手法では、審査プロセスを「Agentic Workflow」により5段階に分解し、各段階ごとに判断確定ステップ(Step)とレビュー本文の品質(Grade)から信頼性スコアを算出した。このスコアに基づいて、人とAIの判断が高い一致を示す自動承認可能な範囲(HAZ)を定量的に明示した。実運用データ20万件の評価では、信頼性スコア0.15以下の領域で人とAIの一致率が100%(95%信頼区間下限でも99.997%)を達成し、全体の約60%をAIが自動承認、従来最大7日を要した処理を10分以内に短縮した。HAZはAIに安全に判断を委ねる新たな枠組みとして、従来のHuman-in-the-Loop(HITL)に代わる指標となり得る。本研究は、信頼性スコアモデルとHAZの構造化によって、AI社会実装における設計思想と現場運用をつなぐ先駆的事例である。
AIの業務適用が進展する現代において、「どこまでAIに判断を任せられるか」は重要な課題である。本研究では、人とAIの判断が一致する領域をHuman-AI Agreement Zone(HAZ)と定義し、それを信頼性スコアとして抽出、AIが主体的に判断する自動化構造を提案する。対象は年間50万件の商品レビューの審査業務である。本手法では、審査プロセスを「Agentic Workflow」により5段階に分解し、各段階ごとに判断確定ステップ(Step)とレビュー本文の品質(Grade)から信頼性スコアを算出した。このスコアに基づいて、人とAIの判断が高い一致を示す自動承認可能な範囲(HAZ)を定量的に明示した。実運用データ20万件の評価では、信頼性スコア0.15以下の領域で人とAIの一致率が100%(95%信頼区間下限でも99.997%)を達成し、全体の約60%をAIが自動承認、従来最大7日を要した処理を10分以内に短縮した。HAZはAIに安全に判断を委ねる新たな枠組みとして、従来のHuman-in-the-Loop(HITL)に代わる指標となり得る。本研究は、信頼性スコアモデルとHAZの構造化によって、AI社会実装における設計思想と現場運用をつなぐ先駆的事例である。