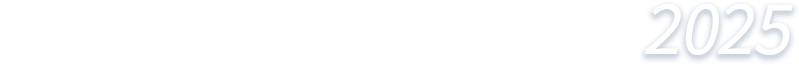併設チュートリアル
実施テーマ・講演者紹介
ソフトウェアプロセス改善の基本
-あなたが改善を進めよう!
総合研究所 デジタルイノベーションテクノロジーセンター
ソフトウェアプロセスイノベーショングループ
概要
品質保証部門や設計開発部門でソフトウェア・システムの品質管理や改善に取り組んでいる皆さん、開発・保守プロジェクトを改善するためにうまくアプローチできていますか?担当しているプロジェクトでの改善サイクルや、複数のプロジェクトを組織全体で改善するサイクルはうまく回っていますか?設計開発と品質保証の部門間の壁を越えて協力できていますか?
ソフトウェアプロセス改善(SPI: Software Process Improvement)活動によるプロジェクトの品質や組織のプロセスを改善するための基本的な考え方、進め方とポイントを学びましょう。改善活動の推進は難しいですが、解決のヒントを持ち帰っていただきたいと思っています。
● 実施形態
オンライン● 定員
16名● 参加者へのお願い
Google ColaboratoryまたはMIROを使用予定
艸薙 匠 氏
業務上の経験や研究を主とした経歴
コーポレートSEPGとして、SEI SW-CMMリードアセッサー、ISO 9001内部監査員、社内SEPGリーダコース/SQAGリーダコース講師などを通じて、社内でのソフトウェアプロセス技術の研究開発及び現場改善推進を一貫して担当。
1998年~1999年度日科技連SPC研究会「普及啓蒙分科会」副主査、2012年度~2014年度でSQiP運営委員会委員。2015年度からJCSQE委員会委員。
研究論文や著書
監訳担当、デイビッド F.リコ (著)、ソフトウェア・プロセス改善のROI: プロジェクト・マネジャーとソフトウェア・エンジニアのためのメトリックス、 2006/11/1その他(学位、表彰、学会活動、その他特記事項)
- 第15回日科技連品質管理シンポジウム(1995年) 論文賞受賞 「ソフトウェアプロセス(再)設計による改善活動」
- 第20回ソフトウェアシンポジウム2000 優秀発表賞 「CMM 活動 - アンケート方式によるプロセス診断改善活動事例紹介」
- 第31回ソフトウェアシンポジウム2011 最優秀論文賞 「プロジェクトの実現可能性の可視化を支援する負荷容量図の提案」
- SPI JAPAN 2014、2017 チュートリアル講師 「基本に立ち返って、SPI活動をブラシュアップしよう! 」
- 日科技連 SQiPシンポジウム2021 チュートリアル講師 「ソフトウェアプロセス改善の基本-あなたがPJの品質を改善するには?」
- SPI JAPAN 2023 LEGO®SERIOUS PLAY® (レゴ®シリアスプレイ®)体験ワークショップ講師
実務としてのSBOM
~作成から活用までのリアル~
ITプラットフォーム事業部 DXソリューション本部
シニアOSSスペシャリスト(本部長)
概要
SBOM(ソフトウェア部品表)は、2021年の米国大統領令でサイバーセキュリティ対策の重要技術として言及されたことを皮切りに、各国政府や業界団体により標準化が進んでおり、我が国でも、国際標準戦略の一環として、SBOMの普及に向けた取り組みが推進されています。政府機関のガイドラインによるSBOM活用の推奨、EU Cyber Resilience ActによるSBOM作成の必須化など、各企業が至急の対応を迫られている一方で、実務的な検討や実用化のための具体的手段の確立は、十分であるとは言い難い状況です。
本講演では、SBOMの作成から活用までの実務を確実に遂行するための具体的なポイントについて詳しく解説します。
● 実施形態
オンライン● 定員
-
渡邊 歩 氏
業務上の経験や研究を主とした経歴
2005年 株式会社日立システムアンドサービス(現 日立ソリューションズ)入社。2011年より、企業におけるOSS活用のコンサルタントとしてプロセス構築やシステム導入などを支援する業務に従事。
2022年 経済産業省によるSBOM実証実験に技術アドバイザーとして参画。
2023年 The Linux Foundation OpenChain Japan Planningリーダーに就任。
2024年 The Linux Foundation Japan初代エバンジェリストに就任。
2024年 株式会社日立製作所のOpen Source Program Officeに初期メンバーとして参画。
2025年 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 専門委員に就任。
研究論文や著書
寄稿:- 日本知的財産協会 知財管理 Vol.71 No.11(No.851) 論説「企業におけるOSSコンプライアンス業務推進に関する考察 - 組織運営、業務プロセス及び人材育成について -」(2021年11月20日発行)
- 日経XTECH 連載「ソフト管理の新常識、SBOM徹底ガイド」
その他(学位、表彰、学会活動、その他特記事項)
研究発表:- 研究・イノベーション学会 第35回年次学術大会 共同発表「日本企業によるオープンソースソフトウェアコミュニティへの貢献に関する考察」(2020年11月1日)
- 日本知財学会 第18回年次学術研究発表会 共同発表「オープンソースソフトウェアコンプライアンスに関するスキル標準のフレームワークに関する研究」(2020年11月28日)
要求定義
~要求品質と仕様品質を高める実践手法~
代表
概要
組込みシステムの大規模化/複雑化が進むが要求開発が個人に依存した開発になり仕様品質の改善が困難な状況になっている。
本講座では、ステークホルダーに最高の価値を提供する要求開発の実践的な進め方を提供する。更に価値の高い要求を抜け漏れなく曖昧性を無くし高品質な仕様を高効率で定義する実践的な仕様定義技法をご紹介する。サンプル事例を用いて要求開発の実践演習や仕様定義の実践演習を通して実開発での活用を目指す。目的を意識することで自主性向上と開発作業の質の向上も座学と演習を通して学び組込みシステム産業界の発展に寄与できる人材開発を目指す。
● 実施形態
集合● 定員
調整中● 参加者へのお願い
Officeが使用可能なPCを使用予定
岩橋 正実 氏
業務上の経験や研究を主とした経歴
宇宙防衛民生のソフトウェア開発を経て大手電機メーカで空冷/FA事業を経て全社の設計支援/人材開発を推進後、イワハシ工学として開発現場の課題解決支援を推進中。主な専門技術テーマは以下。- 品質/生産性改善(ビジネス要求定義から全プロセス改善とマネジメント改善)
- ソフトウェア開発作業のライン化による生産性/品質改善
- ソフトウェアアーキテクチャ開発とフレームワークの全製品群への適用開発
- 不具合真因分析に基づく未然防止手法の確立と実開発での運用支援
- 要求開発/定義手法の開発と実開発での運用支援
研究論文や著書
1998年に提唱したオブジェクト指向の開発方法論AOO: Autonomic architecture baseObject-Oriented Development Techniquesを現在は、システム開発手法APD(Autonomicand Purpose base system Development methodology)として技術支援及び講演等にて組込みシステム産業界の発展に寄与できるよう活動中。
TECHI Vol.12 リアルタイムシステム実現のための自律オブジェクト指向,CQ出版,(2002)オブジェクトの自律化と競合解決に基づく組込みオブジェクト指向開発手法の提案,情報処理学会組込みシステムシンポジウム2009論文集,pp.81-86(2009)
その他(学位、表彰、学会活動、その他特記事項)
経済産業省 組込みソフトウェア開発力強化委員(スキル、エンジニアリング)その後IPA SEC 連携委員として組込みソフトウェア業界を支援。
ETSS,ESPR,ESMR,ESDR,不具合未然防止の各WGにてガイド開発。
未知の脆弱性検出技法:ファジングの基礎~実践まで
執行役員 研究開発部 部長
概要
本チュートリアルでは、未知の脆弱性検出技法としてファーストクラスに位置づけられている「ファジング」という技術について、その成り立ちから、ソフトウェアライフサイクルにおける位置づけ、ファザー設計の考え方をご紹介します。また、チュートリアル公判では、AFL(American Fuzzy Lop)を利用して、グレーボックスファジングを実際に体験いただきます(※GoogleColab環境を利用します)
● 実施形態
オンライン● 定員
-● 参加者へのお願い
GoogleColaboratoryを利用します。Googleアカウントをご用意ください。
松木 晋祐 氏
業務上の経験や研究を主とした経歴
独立系ソフトウェアベンダにて、テストオペレータから品質部門統括まで、ソフトウェアテストと品質保証にまつわるさまざまなロールを経験後、ベリサーブ/AIQVE ONE へJOIN。ソフトウェア開発、QA/テストにまつわる先進技術推進、応用技術開発を担う部門を創設、運用、ゲーム分野へのAI4QA技術/製品開発等を推進。
東京電機大学 非常勤講師 / テスト自動化研究会 ファウンダー
ISO/IEC/IEEE 29119-9 Co-Editor / JSTQB Technical Committee
W3C CSSWG コントリビューター など
研究論文や著書
著書(共著/共訳)に 「システムテスト自動化標準ガイド」(翔泳社)、「Androidアプリ テスト技法」(秀和システム)、「SQuBOKv2」(日科技連出版社/寄稿) など
初心者のためのやさしいレビュー入門
~レビューの基本と工夫×ChatGPT活用~
品質マネジメント革新部
セクションチーフ
事業本部 システム事業部 開発二部
開発二課 担当課長
概要
レビュー初心者にとって、「何をすればいいのか」「どう指摘すればいいのか」迷うことは少なくありません。本講座では、レビューを“やさしく学ぶ”をテーマに、「これだけは押さえておきたい基本」と「すぐに使えるコツ」を紹介します。演習では、レビュープロセスの中でも“実施”に焦点を当て、「欠陥を見つける力」を鍛えます。さらに、ChatGPTの補助を活用することで、初心者でも重大な欠陥に気づける体験も用意。模擬ドキュメントを使った実践的な演習を通じて、「レビューって楽しい」「もっとやってみたい」と思えるきっかけを提供します。
● 実施形態
オンライン● 定員
-
中谷 一樹 氏
業務上の経験や研究を主とした経歴
研究活動:2010年にSQiP研究会ソフトウェアレビューコースに研究員として参加。2025年からは指導側に回り、研究コース2(ソフトウェアレビュー)の主査としてソフトウェアレビューの研究活動を推進中。研究論文や著書
- 2011 SQiPシンポジウム (中谷 一樹,諏訪 博紀,田邊 哉好,森崎 一邦,末次 努,小田部 健,山本 浩之,牧野 将治,小原 美帆,奥山 剛,細川 宣啓,永田 敦,森崎 修司,間接的メトリクスを用いて欠陥予測を行うレビュー方法の提案)
- 2012 SQiPシンポジウム (川合 大之, 西村 英俊, 添田 建太郎, 小田部 健, 中谷 一樹, 奥山 剛, 菅野 良太, 會見 知史, 上野 直樹, 細川 宣啓, 永田 敦, 藤原 雅明, 森崎 修司, レビューオリエンテーションキットを用いた育成によるレビュー文化の醸成)
- 2013 SQiPシンポジウム (高橋 功,上田 裕之,高橋 実雄,中谷 一樹, 細川 宣啓,永田 敦,藤原 雅明,森崎 修司,HDR法:仮説駆動型レビュー手法の提案-HDR法の実践による生産性と品質の同時向上)
- 2022 SQiPシンポジウム (茂木 郷志,樋口 雄基,宇根 勲,濱田 航一,蜂須賀 夏子,村田 健二,児玉 敬,中谷 一樹,上田 裕之,安達 賢二,ステークホルダーのアクションと関心事に着目したレビュー観点導出手法~今日からあなたも上級レビューア!『SAKE』の提案~)
- 2024 SQiPシンポジウム (北里 竜,片桐 汐駿,馬場 大輔,星野 智彦,中谷 一樹,上田 裕之,安達 賢二,ソフトウェアレビューにおける生成AI活用の研究~ChatGPTが欠陥検出と指摘伝達をアシスト~)
その他(学位、表彰、学会活動、その他特記事項)
- 2011 SQiPシンポジウム Future Award (間接的メトリクスを用いて欠陥予測を行うレビュー方法の提案)
- 2012 SQiPシンポジウム Future Award (レビューオリエンテーションキットを用いた育成によるレビュー文化の醸成)
- 2013 SQiPシンポジウム Best Paper Future Award (HDR法:仮説駆動型レビュー手法の提案-HDR法の実践による生産性と品質の同時向上)
- 2022 SQiPシンポジウム Best Paper Future Award (ステークホルダーのアクションと関心事に着目したレビュー観点導出手法~今日からあなたも上級レビューア!『SAKE』の提案~)
- 2024 SQiPシンポジウム Best Paper Future Award (ソフトウェアレビューにおける生成AI活用の研究~ChatGPTが欠陥検出と指摘伝達をアシスト~)
- 2015-2025 日科技連 SQiP研究会 研究コース2(ソフトウェアレビュー)主査

上田 裕之 氏
業務上の経験や研究を主とした経歴
1996年 株式会社データ通信システム(現DTS)入社。
2017年 DTSインサイトに転籍。
経理系のC/Sシステム開発を皮切りに、WEBシステム、Windowsアプリ、炎上システム、第三者検証など様々なプロジェクトに従事。プログラマーから経歴を積み重ね、現在はプロジェクトマネジメントや営業もこなす。
2012年にSQiP研究会ソフトウェアレビュー研究コースに研究員として参加。ソフトウェア品質向上の面白さにはまって現在に至る。
研究論文や著書
- 2013 SQiPシンポジウム (高橋 功,上田 裕之,高橋 実雄,中谷 一樹, 細川 宣啓,永田 敦,藤原 雅明,森崎 修司,HDR法:仮説駆動型レビュー手法の提案-HDR法の実践による生産性と品質の同時向上)
- 2022 SQiPシンポジウム (茂木 郷志,樋口 雄基,宇根 勲,濱田 航一,蜂須賀 夏子,村田 健二,児玉 敬,中谷 一樹,上田 裕之,安達 賢二,ステークホルダーのアクションと関心事に着目したレビュー観点導出手法~今日からあなたも上級レビューア!『SAKE』の提案~)
- 2024 SQiPシンポジウム (北里 竜,片桐 汐駿,馬場 大輔,星野 智彦,中谷 一樹,上田 裕之,安達 賢二,ソフトウェアレビューにおける生成AI活用の研究~ChatGPTが欠陥検出と指摘伝達をアシスト~)
その他(学位、表彰、学会活動、その他特記事項)
- 2013 SQiPシンポジウム Best Paper Future Award (HDR法:仮説駆動型レビュー手法の提案-HDR法の実践による生産性と品質の同時向上)
- 2022 SQiPシンポジウム Best Paper Future Award (ステークホルダーのアクションと関心事に着目したレビュー観点導出手法~今日からあなたも上級レビューア!『SAKE』の提案~)
- 2024 SQiPシンポジウム Best Paper Future Award (ソフトウェアレビューにおける生成AI活用の研究~ChatGPTが欠陥検出と指摘伝達をアシスト~)
- 2015-2025 日科技連 SQiP研究会 研究コース2(ソフトウェアレビュー副主査)
ソフトウェアメトリクス概論
ソフトウェアエンジニアリング事業部 ソフトウェアエンジニアリング技術第2部
主任研究員
概要
ソフトウェアメトリクスとは、ソフトウェア開発における品質や進捗状況を定量的に評価し、改善や管理に役立てるための手法です。評価の対象には、開発の成果物であるプロダクトと開発の工程であるプロセスの両方が含まれます。本チュートリアルでは、メトリクスに関する初級者に向けて、主にプロダクトを対象とした代表的なメトリクスについて紹介します。また、演習ではプロジェクトのサンプルデータを用いて測定と分析を行い、実践的な活用方法を習得します。
● 実施形態
オンライン● 定員
-
牧 隆史 氏
業務上の経験や研究を主とした経歴
電機メーカーにて長年にわたりハードウェアおよびソフトウェアの設計、要素技術の研究開発に従事。中でも組込みソフトウェアの開発経験が最も長く、コンシューマ向け製品の開発部門において、プロダクトライン開発の導入と併せて、製品全体のソフトウェアアーキテクチャ改善と大規模リファクタリングを推進。研究論文や著書
著書:情報処理教科書「エンベデッドシステムスペシャリスト」(翔泳社)隔年刊 共著研究論文:牧隆史,岸知二,“プロダクトライン開発におけるアーキテクチャリファクタリングの意思決定法”, 情報報処理学会論文誌 Vol.55, No.2 pp.1069-1078, Feb.2014 ほか
その他(学位、表彰、学会活動、その他特記事項)
学位:博士(情報科学)表彰:APSEC2010 Best Industry Paper Award
学会活動:情報処理学会(シニア会員)
その他特記事項:
- JEITAソフトウェア事業基盤専門委員会(2011年~現在)
- 高度ポリテクセンター 組込み・ICT分野 外部講師
- 組み込み適塾(組込みシステム産業推進機構) モデリング概論 講師
最新のテスト戦略入門 テスト戦略を立案してみよう
概要
テスト戦略とは、変化という波を越えるための羅針盤。品質を守るその指針は、状況や価値観に応じて姿を変えます。本チュートリアルでは、ソフトウェアテストの国際標準であるISO/IEC/IEEE 29119を道しるべに、戦略に必要な構成要素と選択肢を紐解きます。演習では、アジャイル開発を題材に、構成要素を選びながら実践的な戦略を各自で考えていきます。
● 実施形態
オンライン● 定員
-
湯本 剛 氏
業務上の経験や研究を主とした経歴
工作機器メーカーにて生産管理システムの構築メンバーを経て、ソフトハウスのテストリーダーとして幅広い分野のアプリケーションの開発に携わる。 その後ソフトウェアテストのコンサルタントとして、テストプロセスの改善、テストツールの導入支援、テスト設計やテスト戦略の教育などに取り組み、現職はfreee株式会社のQAマネージャーとして品質向上に取り組む。副業として株式会社ytte Labを創業し、テスト分析手法である「ゆもつよメソッド」の教育などを行う。博士(工学)。研究論文や著書
書籍:ビジネス主導のテストプロセス改善、現場の仕事がバリバリ進むテスト手法、ソフトウェアテストの基礎、JSTQBソフトウェアテスト教科書、基本から学ぶソフトウェアテスト、ソフトウェアテスト293の鉄則
学術論文:「データ共有タスク間の順序組合せテストケース抽出手法」電気学会 論文誌C Vol. 137 No. 7
国際学会:A Test Analysis Method for Black Box Testing Using AUT and Fault Knowledge など多数
雑誌、ネット記事:日経ITProなど多数
その他(学位、表彰、学会活動、その他特記事項)
JSTQB技術委員ISO SC7 WG26 エキスパート(ソフトウェアテストの国際標準)
AI時代に求められるアジャイル開発の品質と開発生産性
食べログカンパニー 開発本部 品質管理部 部長
概要
近年、アジャイル開発やその派生であるDevOps、開発生産性が注目されています。これは「品質が高ければ売れる」という時代から、「顧客が本当に求める価値を見極める」時代へと変わり、そのための試行を繰り返すプロセスが重要になったためです。
本チュートリアルでは、アジャイル時代に求められる品質の概念がそれまでとどう変わったのかを解説した上で、アジャイル開発で品質を作り込むための「CI/CD、DevOps, AI」といった技術的要素と「アジャイル品質メトリクス、インプロセスQA、シフトレフト」といった品質的要素の活用方法をご紹介します。
● 実施形態
オンライン● 定員
-
荻野 恒太郎 氏
業務上の経験や研究を主とした経歴
新卒で入社したIT企業では、検索エンジンの開発、テスト自動化とDevOpsの推進、IDプラットフォームの開発、SRE部門のマネージャーなどを担当。2014年~2020年ごろまで、システムテストを自動化し継続的に実行する継続的システムテストを推進し、JaSSTやSQiPなどで発表。
2021年に株式会社カカクコムに転職し、レストラン検索・予約サービス「食べログ」の品質管理部門の立ち上げをしつつ、AI時代に求められる品質と開発生産性の融合に取り組んでいる。
研究論文や著書
- 「アジャイル/DevOps開発における品質保証と信頼性」, 日本信頼性学会 論文誌 Vol.42 No.2 2020年3月号 解説論文
- 「Patterns for HR Developing Technical Training」 Asian PloP 2020 共著
- 「QC七つ道具を利用したDevOpsプラクティスの導入による開発とテストの生産性改善」【共著】経験論文 SQiP 2019
- 「特集2 "素早い"テスト実践法」日経SYSTEMS8月号,2017
- 「変革の軌跡 世界で戦える会社に変わる"アジャイル・DevOps"導入の原則」へのDevOps事例「楽天のDevOpsエンジニアのストーリー」の寄稿 2017
- 「楽天でのエンタープライズアジャイルとDevOps」情報処理学会デジタルプラクティスVol.7 2016
- 「安心なサービスの品質改善を実現する為の継続的システムテスト」IPA 先進的な設計・検証技術の適用事例報告書2015年度版
その他(学位、表彰、学会活動、その他特記事項)
ソフトウェア品質管理研究会 研究コース4 「アジャイルと品質」副主査ユーザビリティテストによる利用者視点の重要性理解とUX5階層モデルによる分析演習
ポップインサイトカンパニー
UXデザイナー
ITデザイナ
概要
本チュートリアルでは、ユーザビリティテストとUX5階層モデル分析を体験することで、UXを意識して利用時品質を向上させる方法を学べます。ユーザビリティテストは利用時品質の作り込みに重要です。Webサイトやスマホアプリを実際に利用している状況を利用者視点で観察することで、開発者視点では気づけなかった問題を炙り出し、より使いやすくするための改善案を発想することができます。UX5階層モデルは、戦略・要件・構造・骨格・表層の順に積み上げて利用者のニーズや意向に沿ってUXを組み立てる考え方・枠組みです。ユーザビリティテストで洗い出された問題を5階層に分けて分析することで、UXを損なわないように根本原因から対処できます。
● 実施形態
オンライン● 定員
-
金山 豊浩 氏
業務上の経験や研究を主とした経歴
Webサイト、スマホアプリなどのスタジオでのユーザビリティテストによる利用時品質評価 Zoomを使ったオンライン・インタビューやプロトタイプによるコンセプト受容性評価
SPC研究会(第16年度)〜SQiP研究会(第41年度)において、Webユーザビリティ、ソフトウェア・ユーザビリティ、UX(User Experience)を研究・演習指導。
研究論文や著書
- Amazon Hacks 世界最大のショッピングサイト完全活用テクニック100選(翻訳:ウェブ・ユーザビリティ研究会)https://www.amazon.co.jp/dp/4873111811
- Quality Control Techniques for Constructing Attractive Corporate Websites: Usability in Relation to the Popularity Ranking of Websites Software Quality — ECSQ 2002
- https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-47984-8_9
- SQuBoK V2.0執筆協力(ユーザビリティ、ユーザビリティテスティング)
その他(学位、表彰、学会活動、その他特記事項)
UXPA(User Experience Professionals Association)会員(2012年Asia Regional Director)
HCD専門家(2016年〜) HCD-Net HCD導入パターン委員会メンバー
中級ソフトウェア品質技術者(JCSQE)
Certified Tester, Foundation Usability Testing ASTQB - ISTQB in the U.S.
国家資格キャリアコンサルタント
プロティアンキャリア認定ファシリテーター
ICT支援員